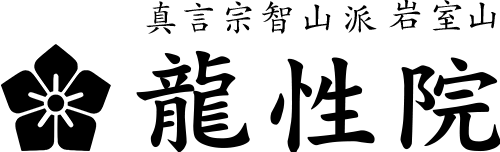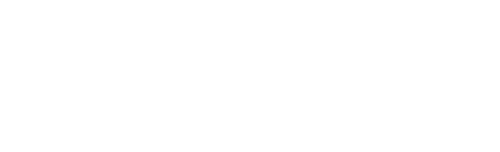-
春彼岸号2018.03.05
一病息災
今年も早いもので、平成30年の新年を迎えてから2か月半ばかり経過をいたしました。
春のお彼岸を前に、季節の変わり目らしい寒暖の差がある落ち着かない天候が続いておりますが、龍性院檀信徒の皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか?
花粉も大量飛散中であり、風邪もまだまだ油断できない今日であります。
何卒体調には十分ご留意いただき、暖かい春をお迎え下さい。
皆様には、常日頃より當山護持のため格段のご信援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この冬は寒さが大変厳しく、さいたま市では1月26日に1977年に観測を始めてから最も低い気温である-9.8℃を記録。
この寒さと空気の乾燥の影響から、国内ではインフルエンザが大流行いたしました。
先ほど皆様に「体調には十分ご留意いただき~」と申し上げましたが、恥ずかしながら私も、今年になってインフルエンザA型に罹患してしまい、数日間休息を取らざるを得ませんでした。
新たな年を迎え、忙しい毎日の中でろくに休息も取っていなかった私にとって、不本意ながらも体を休ませる機会をいただくことになったのです。
数日間の休息の後、体調は快方に向かいましたが、その時感じたのは、インフルエンザに罹患する前より今の方がずっと体が快調になったということです。
また、体の為には無茶は禁物だし、やはり休息は大切だなと改めて学ぶ良い機会になりました。
〝無病息災〟という言葉があります。
病気や災いにも見舞われず、元気に過ごすことを意味します。
さらにもうひとつ、〝一病息災〟という言葉があります。
何かひとつ病気をした人は健康に留意するようになるので、かえって元気に長生きするものである、といった意味です。
無論、無病息災であることが何よりですし、そうありたいものだと思います。
しかし、病気を患ったからこそ気づくこともたくさんあるのです。
私たちは、諸行無常の世界に生きております。
今元気だといって将来も安心ではないし、病気だからといって将来も絶望ではないのです。
大切なのは、現状をしっかり見つめ、学び、これからの生活にどう活かすかということではないでしょうか?
この〝一病息災〟には、私たちが心豊かに過ごすためのヒントが込められていると私は思います。
今年インフルエンザになった方も、そうでない方も、現状を見つめ、学び、今までの経験を今後に活かしてお過ごし下さい。
-
正月号2018.01.01
加点と減点
新年おめでとうございます。
龍性院檀信徒の皆様方におかれましては、平成30年の新しい年をご家族ご一同様でご無事にお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
また、昨年中に皆様方に賜りましたご厚情に対しまして、心よりお礼を申し上げます。
さて、先月のことですが、学生時代の友人数人と久しぶりに食事に出掛けました。
美味しい料理を囲みながら、学生の時の話で盛り上がっていた時、友人のひとりがテストの点数に話題を向けました。
その友人は、俗に言えば大変勉強が得意であり、テストで一度70点代をとってしまった時に、もうどうしようもなく落ち込んでしまい、しばらく立ち直れなかったという話でした。
勉強が得意でない者からすれば嫌みに聞こえるかもしれませんが、彼は本当に落ち込んだと真剣に話してくれました。
その話を聞いていたもう一人の友人は、「俺だったら、70点代とれたら万々歳だよ!」と答えました。
私は、そのやり取りを聞いて、なるほどな~と納得し、箸を進めていました。
テストの点数は同じ70点でも、ある者からすれば立派な合格点であり、またある者からすれば落第点に等しいと感じる。
人間の心、感受性は実に様々だなと感じました。
テストに限らず私たちは常日頃、さながらテストの点数の如く、自らや他人の事について心で採点を下しながら生活をしています。
食事にしても、口に運び自らの経験と判断の元に、美味しいとか不味いと判断し、採点しています。
人間関係にしても、「この人はこんなにいいところがあるけど、ここがダメだ!」と他人を採点します。
この採点の方法には、加点式と減点式の二つがあります。
先ほどの70点で落ち込んでいた友人は、70点という点数を減点式でとらえているのだと思います。
もともと100点満点のはずのなのに、30点分も間違ってしまったという考え方です。
一方、もう一人の70点で万々歳の友人は、もともとは0点のところ70点分も正解できたという加点式の考え方です。
私は、この二つの考え方のどちらが正しく、どちらが間違っているということを言いたいわけではありません。
確かに、100点を目指そうと思えば楽観的に物事を考えるだけでなく、どこで30点間違ったのか、きちんと向き合うことは大切です。
しかし、70点をとったことで、しばらく立ち直れないほどに落ち込むというのであれば、そこは加点式で事実を受け止め、次回に向け前向きに努力を重ねていくのが、その方の為ではないかと感じます。
人についても、どうしても私たちは減点式で判断しがちです。
自分も含め、100点の人間なんてそうはいるものではありません。
自分や他人、すべてのものの良いところを加点してみる心を養えれば、今まで以上にゆとりをもって過ごせるのではないでしょうか?
年頭に当たり、皆さまのご健勝、ご多幸をせつにお祈りいたします。
-
お盆号2017.07.02
施しのこころ
7月になりました。
早いもので、平成29年も半分以上の月日が経過したということです。
この季節らしいジメジメした陽気と共に、一日を通じ時折雨が落ちる、梅雨真っ只中といった日々が続いております。
檀信徒の皆様には、何卒御自愛いただき、猛暑と予想される今年の夏もお元気にお過ごし下さいます様、ご祈念申し上げます。
さて、今年も後1ヶ月余りでお盆の時期を迎えます。
お盆の期間(8月13日~16日)はご先祖様をご自宅に迎え、年に1度のご先祖様の里帰りを皆でもてなしたいものです。
當山では、このお盆期間中の8月14日に毎年恒例の大施餓鬼会(だいせがきえ)を行います。
大施餓鬼会というとわかりにくいかもしれませんが、〝お施餓鬼(せがき)〟と聞くとおわかりになる方も多いのではないでしょうか?
多くの僧侶が集まり本堂内に読経が響き渡る中、新盆を迎える家族・親族を始め、毎年大勢の檀家の皆様がお詣りをし、ご先祖様に塔婆を上げてご供養をする大変重要な法要です。
そもそもこの施餓鬼とは、お釈迦様の十大弟子のひとり阿難尊者(あなんそんじゃ)の古事に由来したものであり、餓鬼に食べ物を施すことを言います。
餓鬼とは、死後生まれ変わるとされる六道(①天道・②人間道・③修羅道・④畜生道・⑤餓鬼道・⑥地獄道)の餓鬼道に住んでおり、常に飢えや渇きに苦しみ、例え食物や飲み物を手に入れたとしても口に運ぼうとすると焔に変わってしまう、満たされざるものです。
この餓鬼をさらに、〝無財餓鬼(むざいがき)〟と〝有財餓鬼(うざいがき)〟という2種類の餓鬼に大別することができます。
無財餓鬼とは、まったく何も口にすることができない餓鬼です。
上記の通り、たとえ目の前に飲食物があったとしても、食べようとすると発火し食べることができないのです。
一方、有財餓鬼とは食事をとることができる餓鬼を言います。
有財餓鬼は、不浄なるものを少量口にできる〝少財餓鬼(しょうざいがき)〟と、多くのものを飲食できる〝多財餓鬼(たざいがき)〟とにさらに分別をされます。
多財餓鬼に至っては、多くの食事がとれるばかりでなく、六道の天道にも行くことができる恵まれた餓鬼なのです。
ただし、無財餓鬼にも多財餓鬼にも共通しているのは、満たされざるものであるということです。
食事をまったくとれない無財餓鬼はもちろんのこと、たくさんの食事ができる多財餓鬼もけっして満腹にはなれないのです。
このような恐ろしい餓鬼の世界ですが、それでは私たちが生きている世界はどうでしょうか?
食事をとれないくらい貧しい方は、世界を見渡せばたくさんいらっしゃいます。
また、多くの食事や快適な生活に恵まれながらも、けっして満足できない満たされない方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか?
餓鬼の住む恐ろしい世界は、今を生きる私たちのすぐ身近にあるものなのです。
さて、説明が長くなってしまいましたが、施餓鬼とはこの満たされざるものに食べ物を施し救う為の法要です。
あらゆる餓鬼に施しを与えることにより自らの心を養い、その功徳が施主や今は亡き先祖に及ぶものなのです。
私たちの心には、多少なりとも餓鬼の心は存在します。
しかし、その心に支配をされてしまっては、私たちは完全な餓鬼道へと堕ちてしまうでしょう。
そうならない為にも、施しのこころを学び、仏様の心に近づけるよう精進したいものです。
皆様の、大施餓鬼会へのご参詣をお待ちしております。
-
正月号2017.01.01
新年のご挨拶

平成28年もあっという間に過ぎ去り、新年が始まります。
龍性院檀信徒の皆様方におかれましては、平成29年の新しい年をご家族ご一同様でご無事にお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
昨年中に皆様方に賜りましたご厚情に対しまして、心よりお礼を申し上げます。
また、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、ここ数年の龍性院だより正月号では、まず昨年一年間に起きた出来事等を振り返り、お話をさせて頂いておりますので、今回もそのようにさせて頂きたいと存じます。
昨年を振り返りますと、国内では4月14月に熊本県、大分県を中心に最大震度7の非常に大きな地震が発生し、2日後には本震とされる揺れを観測。
以降、大きな余震が続き、この地震での直接死者数は50名、避難生活からくるストレスや病気でなくなった関連死の方を含めると、100名以上の尊い人命が失われました。
また、8月に相次いで発生した台風により、とりわけ北海道や岩手県は甚大な被害にみまわれました。
北海道に3つの台風が上陸したこと、東北地方太平洋側に台風が上陸したことは、気象庁が1951年に統計を開始して以来、初めてのことだそうです。
この豪雨に伴い住居への浸水被害、河川の氾濫、土砂災害が発生し、岩手県、北海道等で20名近くの方が亡くなられました。
改めまして、被災をされました方々に心よりお見舞い申し上げ、お亡くなりになられました皆様のご冥福をお祈りいたします。
日本はもともと自然災害の多い国と言われます。
全世界の中で日本の国土が占める割合は、わずか0.3%弱ですが、全世界で発生しているマグニチュード6以上の地震の20%以上が日本で起こっているそうです。
それに関連して、活火山も多いわけですから、全国大体どこに行っても温泉が涌き出ていたり、最近ではクリーンエネルギーとして地熱発電が注目をされていますが、これも活火山があるお陰さまでもあるのです。
確かに地震というデメリットはありますが、少なからずメリットも享受をしているわけです。
私たちは、自然の中で、自然の恵みを頂いて生かされています。
なので、自然が無くなれば当然生きていくことはできません。
自然が無ければ生きていけない私たち人間が、自然の営みの中で発生する自然災害からのみ逃れることは無理なのかもしれません。
ですから、逃れられない災害から少しでも身を守る備えは必要ですし、備えていても不幸にもお亡くなりになってしまう方がいることは、遺憾にたえません。
不幸にも亡くなってしまった方を鎮魂する、それが私たち生きている者にできることです。
しかし、自然災害が起こるからと言って、自然を悪だと思うべきではないと思います。
物事には〝裏〟と〝表〟があります。先ほど申し上げましたように、生き物は自然によって殺されてしまう事もありますが、
普段は自然に恵みを頂き生かさせてもらっているのです。私たちは何かあると、物事の悪い方を印象深く残してしまいがちですが、何事も良い部分もあれば悪い部分もあるのです。
それが私たちの生きている〝世界〟なのです。
物事の良い部分は、とかく陰に隠れて見えにくいものです。
しかし、何事にも、どんな方にでもある〝お陰さま〟を常に見つける正しい眼を持つことができれば、今までより清々しい世界が開けるのではないかと思います。
年頭に当たり、皆さまのご健勝、ご多幸をせつにお祈りいたします。
-
お盆号2016.07.10
当たり前
はっきりとしない雲の多い日が続いております。
もっとも、梅雨の季節でありますし、それが当然と言えば当然なのでしょうが。
しかし、梅雨といっても今年はあまりまとまった雨は無く、利根川上流にあるダムの貯水率は軒並み平年を下回っており、1992年の観測開始以来最低の貯水量と言われております。
関東地方では、1994年にも雨が少なく水不足となり、東京で渇水対策本部が設置され、取水制限も最大で15%行われました。
今年も今後の雨量次第では、取水制限が実施され、給水制限や、もしかすると断水ということもありえるかもしれません。
水を無駄にせず、大切に使うことを今から心がけておく必要があるかもしれませんね。
私たちは普段生活をしている中で、水を飲みたい時、トイレに行きたい時、お風呂に入りたい時、いつでも当たり前に水を使えると思っております。
今年も水不足と騒がれてはいても、まだ今の時点(7月10日現在)では、蛇口を捻れば普通に水は出ますし、生活に何ら支障をきたすことはありません。
しかし、このまま雨がダム近辺にあまり降らないと、いよいよ給水制限や、最悪の場合、断水もありえるわけです。
そうなると、私たちの生活にも支障が出て参ります。
トイレに行っても時間によっては水を流すことも出来なくなるかもしれません。
お風呂に入りたくても、シャワーが出なくなるかもわかりません。
のどが渇いても、水を飲めないかもしれません。
水が不足するということは、実に恐ろしいことなのです。
しかし日本に於いては、とりわけ関東地方に於いては、水が不足するというのはそう頻繁に起こるものではありません。
ですから、どうしても私たちは普段、水があるのは当たり前と思ってしまうわけです。
ですが、一度雨が降らなくなれば、私たちが当たり前と考えていることは、あっという間に覆されてしまいます。
当たり前に過ごしている日常さえ、当たり前で無くなってしまうのです。
そう、この世の中には当たり前のことなんて無いのだと思います。
それでは、当たり前のことが無いとなると、この世の中はいったいどんなものなのか、どう考えるべきなのかと皆様思われるのではないでしょうか。
私は、当たり前の対義語の意味する言葉で表すことができるのではないかと思います。
それは、〝有り難い〟という言葉です。
〝有り難い〟という字は、「有ることが難しい」とも読むことができます。
私たちが日常当たり前だと思って過ごしているこの環境は、すべて有り難いものなのです。
ですから、当たり前のことは無いのですから、毎日をいつも通り普通に過ごせるのも実は本当に有り難いことなのです。
仏教では、すべてのものに感謝する心を養うということを大切にします。
それは、私たちが幸せに生きていく為には、すべてのものに感謝する心が必要だからです。
いつも通り、朝無事に目が覚めて、いつものように朝食を食べ、仏壇に手を合わせ、学校や仕事に出かけ、夜になれば家に帰り、お風呂に入りフカフカの布団で眠る。
こういった日常を、すべて〝有り難い〟と心で思えたなら、感じることができたならば、それはどんなに幸せなことでしょう。
どうか、これからお盆を迎えるにあたり、龍性院檀信徒の皆様におかれましては、すべてのことに感謝する心を育んで頂き、心安らかに日々をお過ごし頂けますと、幸甚に存じます。
これから暑い日が続くと思われますが、くれぐれも体調に留意して頂き、お盆には元気な姿でお会いしましょう。
-
最近の投稿
-
アーカイブ
- 令和7年3月 (1)
- 令和7年1月 (1)
- 令和6年3月 (1)
- 令和6年1月 (1)
- 令和5年8月 (1)
- 令和5年3月 (1)
- 令和5年1月 (1)
- 令和4年12月 (1)
- 令和4年3月 (1)
- 令和4年1月 (1)
- 令和3年8月 (1)
- 令和3年3月 (1)
- 令和3年1月 (1)
- 令和2年7月 (1)
- 令和2年3月 (1)
- 令和2年1月 (1)
- 令和元年7月 (1)
- 平成31年3月 (1)
- 平成31年1月 (1)
- 平成30年7月 (1)
- 平成30年3月 (1)
- 平成30年1月 (1)
- 平成29年7月 (1)
- 平成29年1月 (1)
- 平成28年7月 (1)
- 平成28年3月 (1)
- 平成27年7月 (1)
- 平成27年3月 (1)
- 平成27年1月 (1)
- 平成26年8月 (1)
- 平成26年1月 (1)