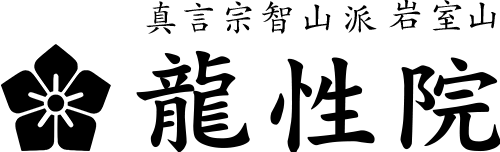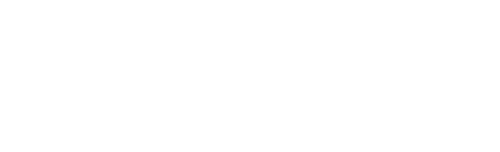-
春彼岸号2025.03.27
彼岸を迎え
ここ数年は暖冬が続いておりましたが、この冬は久しぶりに冬らしい寒い日も多かった様に感じます。冬が寒ければ寒いほど、春の暖かさが一層恋しく思いますが、ここへ来てその春の訪れを日に日に感じる様になりました。常夏の国にいれば、温かいとか暑いとかは“普通”であり、時に涼しいや寒いを恋しくも感じます。今、日本へのインバウンドが人気ですが、東南アジアなど暖かい国の方はあえて冬に訪れて、雪を見たり雪に触れたりする事を楽しむ方も多いようです。我々は、寒い冬を抜け春の訪れを待ち遠しく思いますが、ずっと暖かい国におれば、冬のある国が羨ましくも感じるのでしょう。そういう意味に於いては、四季があり、春夏秋冬の季節ごとに気候も変化し、多様な環境と自然を体感できる日本という国は、非常に恵まれた国であるのかもしれません。
思えば私たちの感覚というものは、すべて相対的であるように思います。暖房の効いた部屋から、暖房の無い部屋へ移動すれば寒いと感じますが、寒風の吹く外から家に入れば、たとえそこが暖房の無い部屋だったとしても暖かいと感じるでしょう。学生だった頃、長い長い夏休みがいつまでも続けば良いと思いましたが、今思えば学校生活があればこそ、また長いお休みが恋しかったのであり、毎日がずっと休みであったら、休みの有難みというものも感じなくなってしまうのでしょう。一日に一食しか食べられない人が二食食べられるようになったら嬉しいでしょうが、一日三食食べられていた人が一日二食になったら不満になります。どんな環境でも、見方を変えればすべて価値は変わってしまって、絶対的な価値はないのだなとわかります。
日本人は、感謝の心を言葉で表す時「ありがとう」って言います。「ありがとう」の語源は仏教の「有り難し」という言葉です。見方を変えればすべての価値が変わる世の中にあって、人さまから親切にして頂いたり、何気なく過ごしている毎日が、実は本当に有ることが難しい特別な事で感謝すべき事だと、昔の日本人はわかっていたのでしょう。
いつまでも生きていたいと思います。でも、いつかは私たちもご先祖様のもとへ帰ります。いつかは帰らなきゃいけない場所があるから、今の私たちの命も本当に有り難い特別なものだと感じる事ができます。何事にも感謝する心が、私たちの幸福感を育みます。お彼岸にあたり、今一度ご先祖様や自分の命、周囲のすべてに感謝する心を育てたいですね。
-
春彼岸号2024.03.27
彼岸を迎え
「あっ!」という間に日々は流れ、気が付けばもう春のお彼岸を迎える頃となりました。この冬は記録的な暖冬でありましたが、日本のみならず世界的にも暖冬傾向で、米海洋大気局(NOAA)の発表する2月の世界平均気温は過去最高になる見通しだと言われています。三月に入り、寒の戻りと思える日もありましたが、全体としてはやはり暖かい冬であったと感じる方も多いのではないでしょうか?しかし、この寒暖差が激しい気候は体には大きな負担となります。皆様も体調など崩さぬよう、くれぐれもお気を付けください。
さて、日本では年に2回お彼岸があります。3月の春分の日、9月の秋分の日を中日とし、それぞれ7日間に亘ります。近年は気候変動もあり感じにくくなっておりますが、昔から“暑さ寒さも彼岸まで”と言われるように、四季の豊かな日本にとっては、寒さの厳しい冬から暖かい春へ、暑さの厳しい夏から涼しい秋へ、気持ちの良い季節へ移行していく喜びを実感できるのも、ちょうどこの頃ではないでしょうか?
彼岸とは、サンスクリット語の「パーラミター」という言葉が元になっており、正しくは到彼岸と言います。苦しみの原因である迷いや悩みに満ちた岸(此岸)から、苦しみを脱した仏さまの岸(彼岸)に到るという意味です。
ご先祖様が生きていた頃、冬がどんなに寒くても、夏がどんなに暑くても、現代のような冷暖房のある家や、機能性の高い衣服があったわけでもなく、季節によっては決して快適ではない日常も多かったのではないでしょうか?でも、だからこそ、寒い冬や暑い夏から、待ちに待った暖かい春や涼しい秋へ移行し快適になるこの時期に、苦しみの此の岸から悟りの彼の岸へ渡る彼岸という考え方に、自然と得心がいったのだと私は思います。
お彼岸には、是非皆でお墓参りをしましょう。お墓は、亡き人と私たちを繋ぐかけがえのない場所です。亡くなった人と残された人、双方の為にあるものだと感じます。此の岸は、迷いや悩みが多い世界ではありますが、墓前で手を合わせ、ご先祖様と自分の命の繋がりを心に感じることができたなら、どれだけ頼もしく力の湧くことでしょう。そして、仏さまやご先祖様があなたのすぐ近くにあると信じた時、彼の岸もきっとすぐ近くにあるはずです。
-
春彼岸号2023.03.26
栄養
新たな1年が始まったと思えば、“もう”3月を迎えました。時がたつのは本当に早いものです。さらに、この2週間程は“まだ”3月だとは思えないほど暖かい日も多く、1ケ月以上季節が進んだような陽気となっています。この調子だと、お彼岸の頃には桜の花を楽しむ事が出来るかもしれませんね。
春を迎ると様々な花は咲き誇り、木々は一斉に青葉に覆われます。冬の寒さに耐えた後、木々や花が元気に育つ姿を眺めていると、何だかこちらまで元気をもらえるような、明るい気持ちになります。若く青々とした葉は本当に美しいものです。
一方、私は以前、木枯らしに吹かれて落ちた葉を見ると、何か物寂く切ない気持ちになっていました。
しかし、ある時に知り合いの方(仮にAさん)から、「木枯らしによって木の枝から枯れ葉が落ちるという事は、次の葉が生まれる準備が整ったっていう事だよ」と教えて頂きました。さらにAさんは、「枯れて落ちた葉は、腐って栄養を含んだ土になって、その土が木の根に栄養を届けるから、若葉が育ち立派な青葉を茂らせるんだよ」と続けました。不勉強だった私は、その話を聞いて温かい気持ちになり、その後は落ち葉を眺める時の気持ちが変わりました。
枯れた葉は、自らの役目が終わってただ散るのではなく、落ち葉となった後も、次の若葉の為の土となり、栄養を送り育て上げているのです。自然は、そうしてちゃんと長きに亘って命を繋いで今に至っています。
翻って、私たちは木々の落ち葉と同様に、自分もやがては枯れて落ちた後、次の世代を育てる栄養となる、そんな風には普段あまり考えないものです。まして、今の自分が葉をつけて生きて来れた事は自分の力のお陰であり、前年の落ち葉の栄養のお陰様とは、ほとんど考えないでしょう。しかし、人だって落ち葉の栄養が無ければ、決して葉を茂らせる事はできないのです。
間もなく、春のお彼岸を迎えます。お彼岸には、是非皆でお墓参りをし、ご先祖様に手を合わせましょう。ご先祖様は、今の私たちが葉をつける栄養になってくれています。感謝の想いを伝え、頂いた自分の命を精一杯輝かせましょう。その心が、やがて次の葉が育つ為の栄養となります。自然が教えてくれています。自然の木々がそうであるように…
-
春彼岸号2022.03.17
平和を願って
今年も、ようやく春らしい暖かさを感じる日が増えて参りました。今シーズンの冬は、特に新年を迎えてから冷え込みの強い日が多く、首を長くして春の訪れを待っておりましたので、最近のポカポカ陽気を個人的に非常に嬉しく感じる今日この頃です。
さて、いよいよ春を迎え、新しい年度のスタートへと心新たに明るく進んで参りたい想いですが、世界へ目を向けると暗い戦争の話題が影を落とします。
2月24日、ロシアがウクライナへ侵攻を開始し、戦争が勃発しました。ウクライナは、ソ連崩壊とともに独立を果たした国です。ロシアの立場からすると、ウクライナは元々ロシア帝国の一部であり、またソ連時代も一緒だったという観点から、自国の勢力下に置きたいとの考えがあり、ウクライナのNATOへの加盟を阻止する為、戦争を始めたのでしょう。
日本を始めとした多くの国が、このロシアによるウクライナ侵攻を非難し、ロシアへの経済制裁やウクライナへの支援を行っています。そうしたウクライナ側に就く国々に対し、ロシアのプーチン大統領は核兵器の使用も辞さないと思わせる発言を行い、また、ウクライナ国内にある原子力発電所を攻撃する等、世界中を緊張と恐怖に陥れています。
お釈迦様の時代にも戦争はありました。お釈迦様はこうした戦争が起こってしまう現実に対し法句経で次のように説かれています。
「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みをもってしたならば、ついに怨みのやむことはない。怨みを捨ててこそやむ。これは永遠の真理である。」
今の私たちが聞いても、その通りだと感じます。第2次世界大戦の後、サンフランシスコ講和会議にて、日本への戦後賠償に対し各国で話し合いが持たれました。その時、セイロン(現スリランカ)代表のジャヤワルダナ蔵相(後の第2代大統領)は、この言葉を引用して日本への賠償請求権を放棄し、当時一部の国々が主張していた日本分割案に反対し、これを退けました。
怨みを捨てることは、簡単ではありません。実際に自分や自分の大切な人が何か被害にあえば、軽々に怨みを捨てるなんてできるわけはありません。しかし、それでも怨みは怨みしか生まないというのが、お釈迦様の説く心理なのです。
ならば、現実に生きる我々は、この教えをどう考え実践していけば良いのか。それは、怨みを決して良いものとせず、仏さまのように他をあわれみ、楽しみを与え、苦を取り除く“慈悲”の心を育むことかと思います。1日も早い、戦争の終結をご祈念致します。
-
春彼岸号2021.03.15
忘れてはいけない事
昨年の記録的な暖冬に比べると、今シーズンは冬らしく冷え込む日もありながら、しかし着実に春の訪れを感じるこの頃となりました。昨年に続き、今年も東京の桜(ソメイヨシノ)の開花予想日は例年より10日も早い予想となっており、寒い冬を乗り越え草木も急ピッチで春を迎える準備を整えている様です。暖かい気候になって来たとは言え、世界は未だコロナ禍の中にあります。檀信徒の皆様は、お変わりなく無事にお過ごしでしょうか?
さて、今年はあの東日本大震災の発生から10年の節目を迎えました。時の経つ早さに驚くと共に、“十年一昔”の言葉通り、最近では東日本大震災が世間でも昔の事となりつつある様に感じられます。しかし、場所によって復興は未だ道半ばであり、実際に被災をされた方や地域にとって、傷を癒すには十分な時間とは決して言えないと思います。
世界では、どこかで毎年のように大きな自然災害が発生を致します。我が国に目を向けても、今年度だけで『令和2年7月豪雨』や、各地での台風・豪雪の被害、今年の2月13日には福島県・宮城県で最大震度6強を観測する地震が起こる等、多くの災害に見舞われました。自然の営みの中で生かされている私たちにとって、自然の営みそのモノである自然災害は今後も向き合いながら生きていくほかありません。
東日本大震災のあの時、直接被災をされなかったとしても、これを他人事や昔の災害とやり過ごすのではなく、いつ起こるかわからない自然災害だからこそ、普段から備えを怠ってはならないのだと思います。
震災時に、“絆”という言葉がさかんに使われました。絆とは、本来動物を繋ぎとめておく綱の事を言いますが、この時は人と人の結びつきや助け合いの意味として多くの方に共有された言葉です。あの時、有事の際人間は一人では生きていけない、お互いに支えあう事が大切だと多くの方が学んだはずでした。しかし今はどうでしょうか?震災についての風化やコロナ禍も相まって、再び人との結びつきが蔑ろになっているように私は思います。
人は忘れる生き物と言います。ある程度は仕方ないのかもしれません。辛い記憶は、むしろ忘れていく事で気持ちが救われる部分もあります。しかし、人間は一人で生きているつもりでも決して一人では生きていけない、これは忘れてはいけない事実です。
震災時、悲惨な被災地の状況にあっても、人々が助け合う姿に多くの方が勇気をもらい、人と人の繋がりのもと再び前を向いて進む事ができました。この事実を、私たちはコロナ禍でも決して忘れてはいけないと強く感じます。
1
春彼岸号 | 宗教法人 龍性院 | 埼玉県比企郡吉見町にある”真言宗智山派岩室山龍性院”のオフィシャルホームページ
春彼岸号